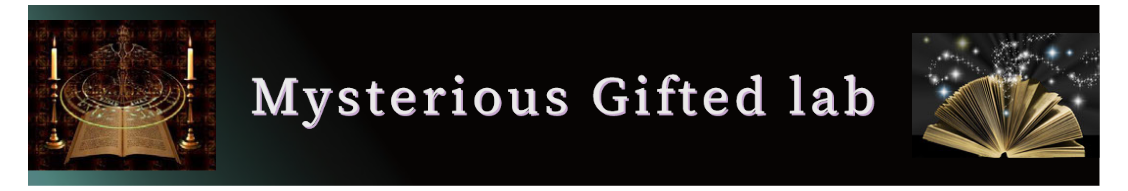この講座で貴方に役立つ内容
・アンセルフィッシュの重要性
・他者貢献によるIQ・EQアップ術
・評価関数の並び替え思考が容易に
・現状の外へとエスコート
・唯一無二の絶対的応援者の獲得
コーチングとは
コーチングを学ぶと、人生が劇的に変わる!?誰もが興味を持つ「特別なスキル」を解説
「コーチング」と聞くと、スポーツの世界やビジネスの現場をイメージする人もいるかもしれません。でも実は、コーチングを学ぶことで得られる力は、私たちの日常生活、人間関係、そして未来を切り開く上で、まるで魔法のような効果を発揮します
1.あなたの中に眠る無限の可能性を引き出す魔法
コーチングとは、相手の目標達成や成長をサポートするコミュニケーションスキルです。ティーチングやアドバイスとは異なり、相手自身が答えを見つけ、自発的に行動できるよう導くことに重点を置いています。
まるで、眠っていた才能や可能性に光を当て、それを開花させる魔法使いのような役割を果たすのが、コーチングを学んだあなたなのです。
2.コーチングを学ぶと、こんな「魔法」が使えるようになる!
具体的に、コーチングを学ぶと、私たちの人生にどんな変化が起こるのでしょうか?
- 人の才能を見抜く「千里眼」:相手の強みや可能性を、本人以上に深く理解できるようになります。「そんな才能があったなんて!」と驚かれることも。
- 目標達成を加速させる「追い風」:相手が本当に望む目標を明確にし、それを達成するための具体的なステップを一緒に見つけ出すことができます。まるで、夢に向かって背中を力強く押してくれる追い風のような存在になれるのです。
- コミュニケーションを円滑にする「魔法の杖」:相手の話を注意深く聞き、本音を引き出す質問をするスキルが身につきます。これにより、誤解やすれ違いが減り、より深い信頼関係を築けるようになります。まるで、人間関係の悩みを解決する魔法の杖です。
- 自信と行動力を高める「勇気の源」:相手の不安や恐れを取り除き、一歩踏み出す勇気を与えられます。「あなたならできる!」という力強い励ましは、相手の背中を押し、行動へと繋げます。
- 自分自身の成長を加速させる「自己啓発エンジン」:コーチングのスキルは、他人だけでなく、自分自身にも応用できます。目標設定、問題解決、モチベーション維持など、自己成長に必要なスキルが飛躍的に向上します。まるで、自分の中に強力なエンジンが搭載されたように、成長スピードが加速します。
- リーダーシップを発揮する「カリスマオーラ」:チームや組織のメンバーの能力を最大限に引き出し、目標達成へと導くことができます。指示命令ではなく、対話を通じてメンバーの自主性を尊重するため、より強い信頼関係とエンゲージメントが生まれます。
3.誰もが主役の人生を
特別な才能は必要ありません。コーチングは、誰でも学ぶことができるスキルです。基本的な考え方やテクニックを習得し、実践を重ねることで、誰もが人を輝かせる魔法使いになることができます。
4.さあ、あなたも人生を変える思考を手にしませんか?
コーチングを学ぶことは、単なるスキル習得ではありません。それは、自分自身と周りの人の可能性を信じ、共に成長していくための、人生を変える旅の始まりです。
もしあなたが、
- 大切な人の夢を応援したい
- チームや組織の力を最大限に引き出したい
- 自分自身の成長を加速させたい
そう願うなら、ぜひコーチングの世界に飛び込んでみてください。きっと、想像以上の素晴らしい変化があなたを待っているはずです。
次のステップの2ndはこちら
講座で使用される用語集
- コーチング:クライアントの目標達成を支援するプロセス。知識やスキルを教えるのではなく、クライアントの内発的な力を引き出し、自己成長を促すことを目的とする。
- コーチ:コーチングを行う人。クライアントの目標達成をサポートする専門家。
- ルー・タイス:1970年代に本格的なコーチングを始めたとされる人物。フットボールコーチとしての経験を基に、教育や企業分野にコーチングの概念を導入した。
- アンセルフィッシュ:他者貢献の意識が高いこと。利他的なという意味合い。ゴール設定においては、個人的な利益だけでなく、他者や社会への貢献を含む目標が重要視される。
- 現状:個人の現在の状況や認識の枠組み。コーチングにおいては、この枠組みを超える「現状の外」のゴールを設定することが重要とされる。
- ブリーフシステム:個人の無意識のレベルで行動や判断を左右する信念や価値観の体系。認知科学の用語。
- 自我:ブリーフシステムを分かりやすく日本語で表現した言葉。宇宙を自分にとっての重要性で並び替える関数として捉えられる。
- エフィカシー:ゴールを達成するための自分自身の能力に対する自己評価。自己効力感とも呼ばれる。コーチングにおいて最も重要な要素の一つとされる。
- エスティーム:自分自身の価値や社会的な立場に対する自己評価。自尊心とも呼ばれる。エフィカシーとは評価の対象が異なる。
- コンフォートゾーン:個人が慣れ親しんだ環境や思考パターン。コーチングにおいては、ここから抜け出し、新しいことに挑戦することが成長につながるとされる。
- アファメーション:目標達成に向けた肯定的な自己暗示。目標達成した状態を現在形で表現し、繰り返し意識することで臨場感を高める。
- 臨場感:まるで現実であるかのように感じる感覚。ゴール達成においては、目標達成後の状態をリアルに想像し、臨場感を高めることが重要とされる。
- ホメオスタシス:生体が内部環境を一定の状態に保とうとする機能。心理的なレベルでも働き、現状維持の力として働く。コーチングにおいては、ゴールの臨場感を高めることで、ホメオスタシスを目標達成の方向に働かせることを目指す。
- スコトーマ:心理的な盲点。重要であるはずの情報が見えなくなってしまう状態。ゴールを設定し、臨場感を高めることで、スコトーマが外れ、チャンスが見えるようになるとされる。